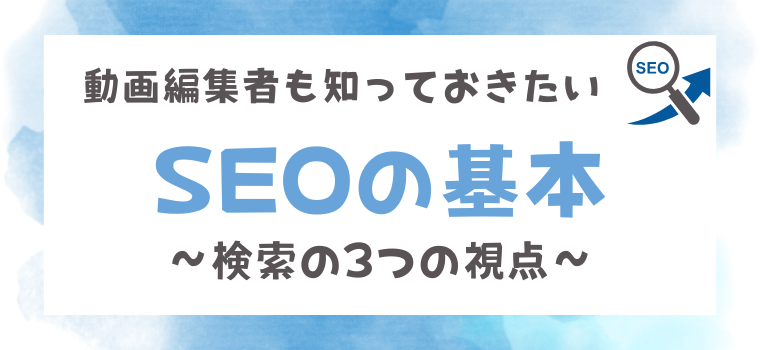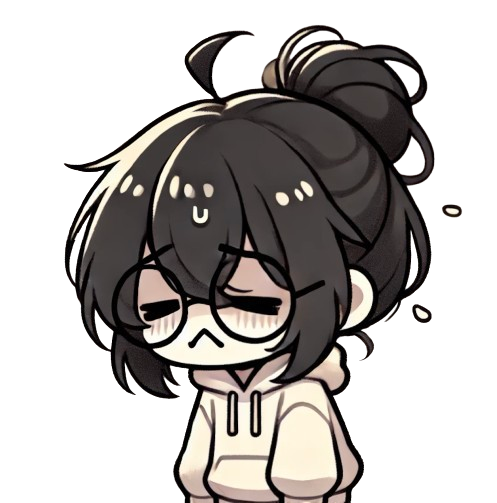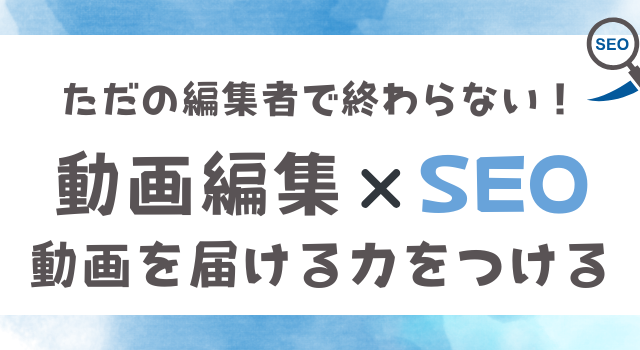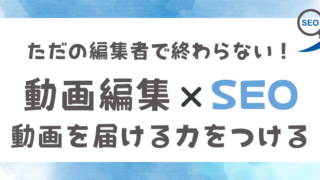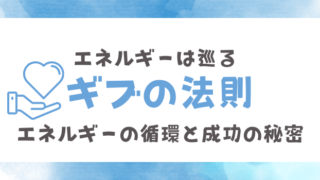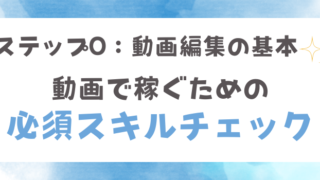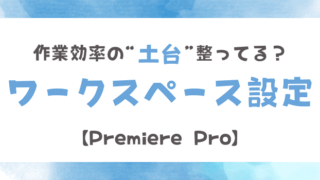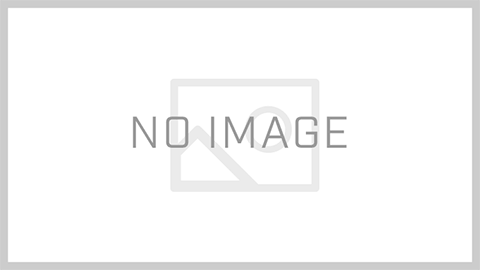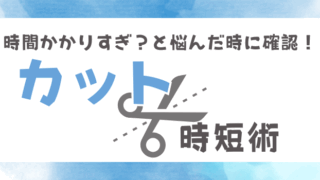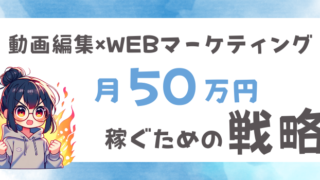こんにちは、動画編集者のあっきゃんです!
「SEOがわかると、何ができるの?」
そんなふうに感じたこと、ありませんか?
SEOの仕組みを知ることで、届けたい情報やサービスが「本当に必要としている人」に届きやすくなるようになります!
例えば、
・情報を届けたい相手に、情報が届くような工夫ができるようになる
・「検索で見つけてもらう」ための視点が持てるようになる
・クライアント様からに、届ける工夫の提案ができるようになる
今回の記事では、テクニックではなく、【SEOの基本の考え方】を中心にお伝えしていきます。
こんな方におすすめ!
- SEOって何?から知りたい
- 自分の情報を必要な人に届けたい
- クライアント様に提案できる知識をつけたい
ぜひ、参考になれば嬉しいです。
SEOってそもそも何?
 SEO(Search Engine Optimization)とは
SEO(Search Engine Optimization)とは
GoogleやYahoo!の検索エンジンで、ページや情報を上位に表示させるための仕組みのことをいいます。
たとえば、「SEO 初心者」と検索したときに、記事や動画が1ページ目の上部に表示されたら、見てもらえる可能性って上がりますよね?
このように、検索結果の上の方に表示されることを「上位表示」といいます。
しかし、ブログやホームページをただ作っただけでは、検索で上位に出てくるのは難しいんです。なぜなら、情報がネット上に溢れているから。
だからこそ、検索結果に少しでも早く、上位に表示させたいと思ったら、「検索される工夫」が必要になります。この工夫のことを「SEO対策」といいます。
SEO(=概念・仕組み)
検索エンジンで情報が表示される仕組みそのもの
検索順位はどのように決まるかの土台の部分。
SEO対策(=行動・実践)
検索結果で上位に表示されるために行う具体的な工夫や取り組み
工夫例
・タイトルに検索されるキーワードを入れる
・説明文をわかりやすく、内容が伝わるようにする
・他と違うオリジナル要素を入れるなど
こうした工夫をすることで、検索エンジンにもユーザーにも「見つけてもらいやすい」情報になります。
検索したあとに、情報が届くまでの流れ
 今や多くの人が、「知りたいこと」や「解決したい悩み」ををGoogleやYahoo!で検索しています。
今や多くの人が、「知りたいこと」や「解決したい悩み」ををGoogleやYahoo!で検索しています。
その検索結果に、あなたの情報やサービスを見つけてもらい、選んでもらうためには、「検索した人にとって有益な情報」だと、検索エンジンやユーザーに認識される必要があります。
そのときに大切なのが、以下の3つです。
SEOで意識すべき3つの視点
①わかりやすさ(Googleのクローラーとユーザーの双方に正しく伝わるか)
②検索意図を考える(検索した人の「知りたいこと」に適した内容になっているか)
③オリジナリティ(他の情報と差別化されているか)
① わかりやすさ
まず大事なのが、「情報が正しく認識されること」
情報を認識してもらうためには、「Googleクローラー(検索ロボット)」と「検索しているユーザー」の両方にわかりやすく伝えることが必要になります。
GoogleクローラーとSEOの関係
Googleクローラーは、Web上の情報を自動で収集・整理して、検索ユーザーにあった情報を届ける役割をしています。
どんなにいい内容であったとしても、クローラーに正しく理解されなければ、検索結果に表示されにくくなってしまいます。
では、Googleはどんな内容を「良い」と評価して、検索上位に表示させるのでしょうか?それはGoogleが掲げている使命と深く関係しています。
Googleの使命
「世界中の情報を整理し、ユーザーがアクセスしやすくすること」
Googleはユーザーが検索した時に、できるだけ早く・的確に、欲しい情報に辿り着けるようにしたい」と考えています。だからこそ、検索意図にあった「役立つ情報」を優先的に上位表示するんです。
Googleクローラーに「この動画はユーザーの求めている情報」「ユーザーのためになる」と認識してもらうには、
- タイトルや説明文に検索されやすいなキーワードを入れる
- 動画の要点がわかる文章を書く、整理する
- 誰に向けた、どんな内容かを明確にする
このような工夫が必要になります。
また、Googleのサービスであるyoutubeはもちろん、Instagram、TikTok、XなどのSNSプラットフォームでも、GoogleのSEOの考え方を取り入れているため、Google SEOの基本を知っておくことは、多くの場面で応用できる力になります。
ユーザーにとってのわかりやすさ
検索エンジンだけではなく、実際に見るユーザーにとっても「わかりやすい」と感じてもらうことが大切です。
ここでいう「わかりやすさ」とは、検索した人が欲しかった答えや情報が的確に得られるか、悩みや疑問を解決できるか。
たとえば、
・知りたいことがすぐにわかった
・最後まで読んだり、視聴したくなる
・納得できて、「これは役だった」「みてよかった」
こうした感想を持ってもらえるかがポイントになります。
なぜなら、GoogleクローラーやSNSのアルゴリズム(おすすめ表示の仕組み)では、以下のような「ユーザーの反応」も評価対象としているからです。
・多くの人が視聴・滞在しているか
(閲覧数や視聴時間)
・シェアされているか
(他の人にも伝えたいと思う内容)
・反応されているか
(高評価、いいね、コメントなど)
これらの反応が多いほど、役立つ情報と判断され、検索結果やおすすめ欄に表示されやすくなります。
アルゴリズムとは
ユーザーの行動データをもとに、最適な動画や情報を選んで表示する仕組み
SEOとは「ユーザーの求めている情報に、適切に応えるための工夫」そのもの。
だからこそ、わかりやすく伝えることで、検索エンジンにも、ユーザーにも見つけてもらいやすくなり、検索結果での上位表示や閲覧数が増えることで、成果につながりやすくなります。
② 検索意図を考える
検索結果に表示されるために、「検索意図」を考えることも大切です。
検索意図とは、ユーザーが「何を知りたくて検索しているのか?」という目的のことです。
たとえ検索結果に表示されたとしても、内容がユーザーの求めているものとズレていたら、
と、離脱されてしまって、「有益な情報じゃない」と評価が下がる原因になってしまうことも。
逆に検索意図にあった内容で、最後まで読んでもらえる・見てもらえる情報になっていれば、GoogleやSNSのアルゴリズムから高く評価されやすくなります。
記事や動画を作る際に意識したいこと
- 視聴者がどんな悩みを持っているのか
- そんな情報を求めて検索しているのか
- その答えを伝えられているか
GoogleやYouTubeの検索アルゴリズムは、ユーザーが求める情報に最も適したコンテンツを優先的に表示するからこそ、「この情報で悩みが解決できそう!」と思ってもらえる内容にしていくことが大事です。
③ オリジナリティ
もうひとつ大事な要素が「オリジナリティ」。
Googleのクローラーは、ただコピーしただけの情報や、他とほぼ同じ内容を評価しづらいと言われています。さらに、他の動画と同じような内容では、検索結果に表示されづらくなる可能性もあるんです。
理由はシンプルで、Googleが大切にしているのは「ユーザーにとって最も役立つ情報を届けること」だから。
ネット上には、すでに似たような記事や情報がたくさんあるので、ユーザーも「また同じ話かも」と感じると、他のページや次の動画に移動してしまう傾向にあります。
だからこそ
と思ってもらえるような「差別化の工夫」が必要になるんです。
オリジナリティを出す3つのコツ
①専門性や権威性
②成功体験や失敗談などの体験談
③統計データ
①専門性や権威性
専門的な知識(医師や弁護士・実務経験者など)や経験を基にした情報を加えることで、他の動画と差別化できます。視聴者は、信頼できる情報源からのアドバイスを求めているため、専門性がある情報は価値を感じます。
②成功体験や失敗談などの体験談
実際に体験した話は共感が生まれやすいです。リアルなストーリーで、親近感を持ってもらえたり、心を動かすきっかけになります。
③統計データ
データや統計を取り入れることで、視聴者にとって説得力が増します。さらに、情報の信頼度のあるデータは、他の方が引用されやすく、拡散や、「良い内容」認知にも繋がります。
おわりに
SEOって聞くと、なんだか専門的で難しく感じるかもしれません。でも本質はとてもシンプル。
「必要な人に、必要な情報を届ける」ための考え方です。
今回お伝えした
・ わかりやすさ
・ 検索意図
・ オリジナリティ
この3つの視点を意識するだけで、検索されやすくなって、あなたの発信やサービスは、「見つけてもらえる情報」に近づきます。
SEOの知識を持つことは、単に「検索上位を狙える」だけではなく、「悩みに対する最適な解決策を、本当に必要としている人に届ける力を持つということです。
たとえば、
- 自分のサービスやスキルが、本当に必要としている人に届く
- クライアント様からの相談に、説得力ある提案ができる
- ただの作業者ではなく、価値を提供できる存在としてレベルアップできる
といったように、「自分の価値を高める」ことができます。
そしてこの考え方は、
編集者・クリエイター・サービス提供者など、どんな働き方でも武器になります。
「この人に任せて良かった」そう思ってもらえる「価値ある存在」を目指して、まずは今日から、少しずつSEOの視点を取り入れてみてください。
最後まで読んでくださりありがとうございます!
また次の記事でもお会いできるのを楽しみにしています。
選ばれる動画編集者にSEOが必要な理由についてもまとめているので、興味がありましたらぜひ見てみてください。