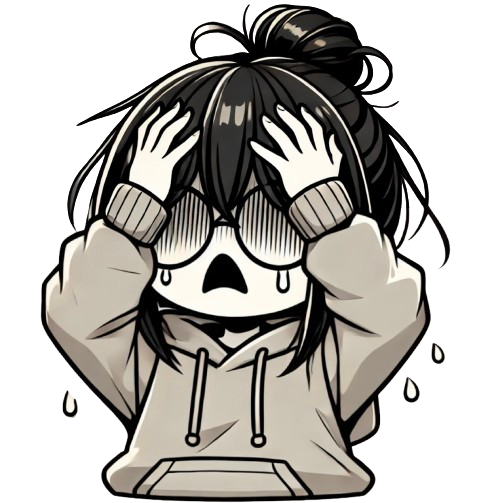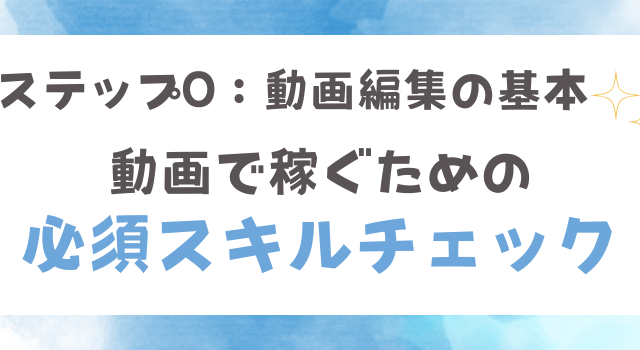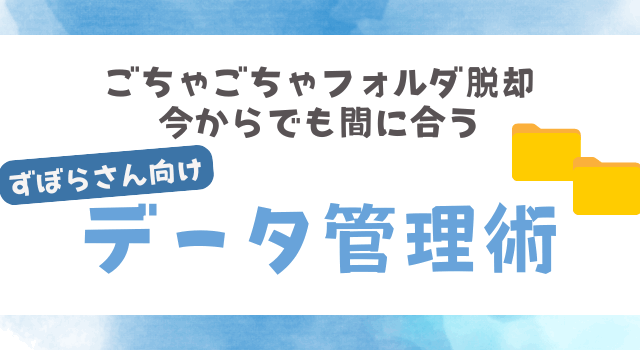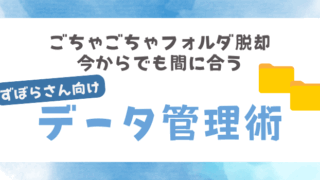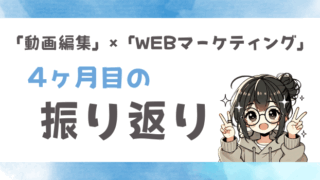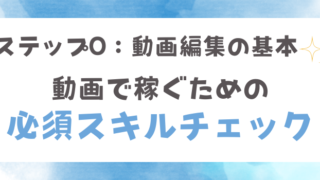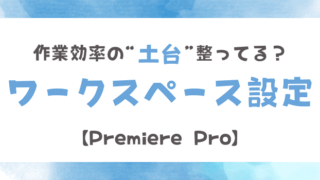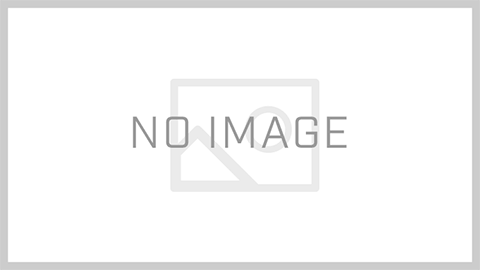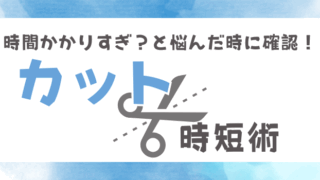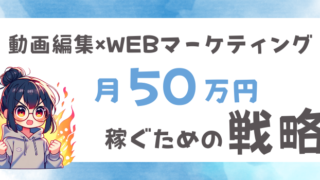動画編集を始めて動画を作ってきて、基本操作にも少しずつ慣れてきたけど、
「いいと思って作ったのに、クライアントに”ちょっと見づらいかも”と言われた」
「そろそろ自己流を卒業して、ちゃんと見やすいテロップを作れるようになりたい」
そんな風に感じる瞬間、ありませんか?
テロップは、動画編集において視聴者の見やすさや理解を助け、動画のクオリティを大きく左右する重要な要素です。しかし、正解がわかりにくく、感覚だけで作り続けてしまうことも少なくありません。
だからこそ今回は、最低限押さえておきたいテロップの基礎についてまとめてみました。
基礎をしっかり押さえることで、
「テロップ作り、なんとなく不安だった…」という状態から、
自信をもって編集ができ、クライアントにも視聴者にも「わかりやすい」「見やすい!」と喜ばれる編集ができるようになります。
この記事で、テロップ作成の土台をもう一度しっかり作り直して、動画編集スキルを一歩レベルアップさせましょう!
テロップとは
動画のコンテンツに魅力を持たせ、視聴者の興味を持ってもらうために、テロップは必要なポイントの一つになります。テロップが加わることで、動画のナレーションやセリフの補助だけでなく、重要な言葉、日付場所などの強調を視聴者に伝わりやすくなったり、盛り上げや感情の表現といった雰囲気作りになります。
テロップの種類
テロップは大きく分けて、テロップは3種類あります。
ショート動画では「基本テロップ」が中心ですが、ロング動画では「肩テロップ」や「紹介テロップ」も合わせて使われることが多いです。
それぞれの役割を押さえて、動画に合った使い方をしていきましょう!
【1. 基本テロップ(テロップベース)】
話している内容をそのまま文字にする、最も標準的なテロップです。ショート動画ではこの基本テロップがメインになります。
例:
「これは今話題の商品です!」など、話しているセリフに合わせた文字
【2. 肩テロップ(表題テロップ)】
動画の中で「今どんな話をしているか」をまとめて表示するテロップです。
ロング動画やインタビュー動画でよく使われます。
例:
「商品の特徴について」
「実際に使ってみた感想」
【3. 紹介テロップ(補足テロップ)】
人物名やお店の名前、商品名など、視聴者に追加で情報を伝えるためのテロップです。
名刺のような役割を持ちます。
例:
「山田太郎(マーケティング担当)」
「〇〇カフェ 渋谷店」
テロップを入れるメリット・デメリット
テロップは動画のクオリティを上げる強力な武器ですが、
使い方を間違えると逆に見づらさや違和感を生んでしまうこともあります。
ここでは、テロップを入れるメリットとデメリットを整理して、
上手に活かすためのポイントを押さえていきましょう!
メリット
視聴者に内容を直感的に理解できる
聴覚だけじゃなく視覚でも情報を得ることができ、理解が深まりやすくなる
視聴者の集中力を高められる
文字があると自然と目線が誘導されて、動画に引き込まれやすくなる
無音環境でも内容が伝わる
通勤中やカフェなど音を出せない環境でも、動画の内容が伝わり楽しめる
実は動画を見ている人の半分以上は音無しで動画を楽しんでいるデータがあります。
動画のリズムやテンポがよくなる
重要な場面に合わせてテロップを入れることで、動画全体の流れがスムーズになる
世界観やブランドイメージを演出できる
テロップのデザイン・フォント・色使いによって、動画の世界観や雰囲気をより印象づけられる
テロップは、単なる文字情報ではなく、「動画をよりわかりやすく、魅力的に演出する」ためのものとなります。内容が分かりやすくなり、最後まで試聴してもらえることで、離脱率を下げ、再生回数やファンの増加にもつながります。
デメリット
作業時間が増える
テロップを丁寧に作る分、編集の工数と時間がどうしても増える
テロップに頼りすぎると映像の魅力が薄れる
→ 文字ばかりで説明しすぎると、映像の力や雰囲気が弱くなるリスクがある
ごちゃごちゃして見づらくなることがある
→ 色、サイズ、位置などのルールがバラバラだと、逆に視聴者が疲れてしまう
コンテンツ内容によっては不要な場合もある
→ 雰囲気重視の映像作品や映画のような作品では、テロップが邪魔になるケースもある
やりすぎや雑につくってしまうことで、ファン化や動画を見てもらう目的と逆の効果になってしまうこともあるため、注意が必要
最低限押さえておきたいテロップ作成のポイント
テロップには正確な「正解」はなく、作り手の感覚や、参考にする人気動画によってデザインや行弦が変わります。しかし、基礎となる部分は大きく変わりません。
ここでは、動画編集初心者〜中級者が抑えておきたい、基本ポイントを整理していきます。
要点だけ入れる
すべての会話をそのまま文字にするのはNGです。
テロップに入れるのは、「視聴者に伝えいたい要点だけ」
視聴者が「理解しやすい」「テンポがいい」と感じるよう、内容をまとめてスッキリ見せることを意識します。
ポイント
話し方や言い回しは統一して、自然な流れを作ることが大切です。
「です・ます」と「だ・である」調を混在させないように注意しましょう。
ただし、話の流れやキャラクターによっては多少崩してもOKな場面もあります。
表記時の注意
テロップを作るときは、文字の表記ルールを統一することで、
視聴者にとって読みやすく、違和感のない動画に仕上げることができます。
ポイント
「、」「。」などの句読点は基本使わない
テロップは流れを止めず、スムーズに読み進めてもらうため、句読点は省略するのが一般的です。どうしてもひつようなときは半角スペースや・などで区切ります。
数字は半角で統一する
「1」や「10」などは半角で統一。全角と半角が混在すると、見た目のバランスが崩れてしまいます。
同じ意味の言葉は表記を統一する
漢字・ひらがな・カタカナ、数字など、バラつきがないように注意が必要です。迷ったときは、一般的な使われ方を参考にすると安心です。
表記統一の例:
× 「1人」「ひとり」「一人」(表記がバラバラ)
○ 「1人」で統一
特にショート動画やSNS用動画では、パッと見た瞬間のわかりやすさが重要です。表記を整えるだけでも、動画全体のクオリティがぐんと高く見えるようになります。
フォントの種類
テロップに使用するフォントは、動画の見やすさや印象を大きく左右します。基本は「読みやすさ」と「世界観に合うこと」を意識して選ぶことが大切です。
ポイント
・基本はシンプルなフォントを選ぶ
無理に凝ったフォントを使うより、視認性を重視することが重要です。
おすすめフォント
【ゴシック体】
ゴシック体ベースが無難で見やすく、くっきり太めの線で、どんな背景にもなじみやすいです。
・源暎ゴシック
文字の視認性・インパクトともにバランスが良く、テロップがさらに見やすくなります。
・源ノ角ゴシック
シンプルでスタンダードなゴシック体。
ビジネス系・解説系など、幅広いジャンルの動画にぴったりです。
・M+
親しみやすさと読みやすさを両立したゴシック体。
カッチリしすぎず、柔らかい印象を持たせたい動画におすすめです。
・Rounded M+
M+フォントの角を丸くしたバージョン。
より可愛らしく、親しみやすい雰囲気を演出でき、エンタメ系やVlogにもマッチします。
【明朝体】
明朝体は、線が細くなる傾向にあり、ゴシック体と比べて視認性が下がりますが、雰囲気が大人っぽく、世界観に合わせて使用されることもあります。
・源ノ明朝
シンプルでスッキリしたデザインが特徴。線が細すぎず太すぎず、ちょうどいいバランスで、視認性が高いのが魅力。小さい文字サイズでもつぶれにくく、スマホ視聴でも読みやすいです。
・ヒラギノ明朝 ProN
プロフェッショナルな印象を与える、きれいで読みやすい。文字の線がシャープで、特にビジネス系や落ち着いた動画にぴったりです。
・游明朝体(Yu Mincho)
Windows標準搭載フォントで、クセが少なくとても見やすいです。
ナチュラルなデザインで、堅苦しくなりすぎず使いやすく、知的で親しみやすい印象を持たせたいときにおすすめ!
【注意点】
おしゃれすぎる細字や筆記体は、視認性が落ち、テロップが読みにくくなってしまうリスクがあるため、基本避けるのが無難です。
どうしても細字・筆記体を使いたい場合は、
背景に色を入れる、影をつけるなどして読みやすさを確保しましょう。
まずは読みやすさが優先です。世界観に合わせたフォント選びで、動画のクオリティも印象もぐっとアップします。
フォントのサイズ
テロップのフォントサイズは、視聴者がパッと見て読みやすいことが最優先です。
特に最近は、スマホで動画を視聴する人がほとんどなので、スマホ画面でもしっかり読める大きさを意識して設定することが重要になります。
ポイント
スマホで見ても読みやすい大きさにする
小さい文字は、気づかれなかったり読めずにストレスになり、離脱の原因になってしまう
目安:文字の大きさは約50pt〜120pt
文字の数によっても異なります。
フォントの色
テロップの色は、視聴者に伝わりやすくするための大切な要素です。ただおしゃれにするだけではなく、「読みやすさ」と「世界観の演出」を両立させることがポイントになります。
テロップの基本は白文字
どんな背景にもなじみやすく、視認性も高いです。
しかし、白文字でも背景が明るかったり、演者の服が白系統ですと、動画素材に埋もれてしまいます。視認性が悪いときは、縁・影・帯をつけることで対策ができます。
背景と反対の色を使う
暗い背景なら明るい文字、明るい背景なら暗めの文字を使うと、自然に視認性が上がります。
このとき注意として、原色は使わないことです。
特にデフォルトで入っている白の「#FFFFFF」や黒の「#000000」は自然にない色で、目立ちすぎて違和感が生じるため、
白は「#FCFCFC」、
黒は「#111111」
など変えてあげることで、動画への違和感を減らすことができます。
使用数
基本的に3色まで、多くても4色以内に抑える
色を使いすぎると画面がごちゃごちゃして、逆に伝わりにくく、チープな印象になってしまいます。
強調したい部分
主に赤や金色を使用されることが多いです。
目立たせたいキーワードにポイントで使うと効果的です。ただし多用するとうるさくなるので、ここぞという場面だけに絞るとより強調されます。
雰囲気に合わせる
ポップな内容なら明るめの色・軽やかな動きの場合は、
オレンジ、黄色、水色などの明るい色で楽しい雰囲気を演出
シリアスな内容の場合は、
ネイビー、ダークグレー、深い赤など、トーンを抑えて重厚感を出して、落ち着いた色・静かな演出
テロップの色も、動画の「世界観」を作る大事なパーツになり、色選びひとつで、動画全体の印象が大きく変わります。
迷ったら、まずは白ベース+黒縁でシンプルにまとめるところから始めると安心です。
フォントの位置
テロップの位置は、動画全体の見やすさと視聴者の疲労感に大きく影響します。場面ごとで位置がバラバラに動いてしまうと、視聴者がどこを見たらいいかわからず、集中の散漫や無意識にストレスを感じる原因になってしまいます。
ただし、強調するために、横テロップを基本に、強調部分は縦にする方法もあります。
基本的な意地を大きく変えすぎないことは意識すると、統一感が出ます。
YouTubeなど横動画の場合は、
基本的に下部固定
セーフティーゾーン内に入れます。(セーフマージンの外側の線より外に出ないようにしていきましょう)
ショート動画の場合は、中央や上部
下部は文字に被ったり、右側のリアクションアイコンと被ったり、下部に集中してごちゃついてしまうため、基本的には真ん中〜上部に入れると見やすくなります。
リールのデッドライン
上:270pix
右:65pix
左:65pix、下部672pixより227pix
下:672pix、右部227pixより768pix
使用する文字数と行数
テロップは、情報を伝えるためのものですが、詰め込みすぎると読みにくくなり、逆効果になります。
ポイント
原則、2行までに抑える
3行以上になると一気に読みづらくなり、スマホ画面だと特に、文字が小さくなったり、情報過多になったりしてストレスになってしまいます。
1行あたり20文字以内
スッキリとして、さっと目に入りやすい量です。
文字の表示時間
テロップの表示時間も、視聴者の「読みやすさ」を左右します
ポイント
1秒で読める量は7〜10文字
人間が自然に読めるスピードを意識して、テロップの表示時間を調整必要があります。
一瞬しかでなかったり、長文なのにすぐ消える=読めない状態になってしまうと、時給換算ことが伝わりません。
もしも話している時間が短く、テロップの表示が難しい場合は、前後の内容に合わせて組み込むことも可能です。
しかし、あえて、短くすることでもう一度見てもらうという手法もありますので、バランスが重要になります。
自分でもみてみて、早すぎて見えなかった、スクリーンショットすらできない早さは酒ましょう。
強調したいワードの目立たせ方
テロップの中でも、特に伝えたいキーワードや重要なフレーズは、強調して視聴者に一発で伝わるようにする工夫が必要になります。
強調する方法
・太字にする
重要な単語だけフォントを太くして、パッと目を引かせる
・フォントサイズを少し大きくする
強調したい単語だけ、周りより少し大きめにするとインパクトが出る
・エフェクトを加える(控えめに)
軽い動きをつけてあげることで、目を引きアピールの効果が出る
【注意】
1つのテロップ内で強調を多用しない
強調箇所が多すぎることで、全体的にゴチャつきがでてしまい、どこを読めばいいかわからなくなってしまいます。
1つのテーマにつき、ポイント1〜2か所までに絞ると、バランスが良くなります。
フォントの入るタイミング
テロップをただ置くだけではなく、「「話している音声のタイミング」と合わせることも重要です。話すタイミングとのズレで違和感を感じてしまうと、見づらくなり、離脱率が高くなりやすくなります。
コンマ単位で、音声の波形を見ながら入れていくのに加えて、実際にみてみて、違和感がないかを確認していきましょう。
おわりに
ここまで、テロップ作成の基礎についてお伝えしてきました。
動画のクオリティを上げるたいと思うと、つい「目立つテロップ」や「凝った演出」をするにはどうすればいいかに意識がいきがちですが、まず大切なのは基本。テロップは、視聴者が動画をスムーズに理解し、見やすくするための大事な要素です。まずは基礎を整えていくことから。
その上で、感情を動かす効果や演出を少しずつ取り入れていくことで、動画編集スキルは高まり、自身の強力な武器になっていきます。
もちろん、最初から難しいデザインや凝った演出を狙う必要はありません。まずは、「見やすさ」と「シンプルさ」を意識して、最低限のルールを守るところからスタートしてみましょう!
最後まで読んでくださりありがとうございました。
次の記事でもお会いできるのを楽しみにしています。