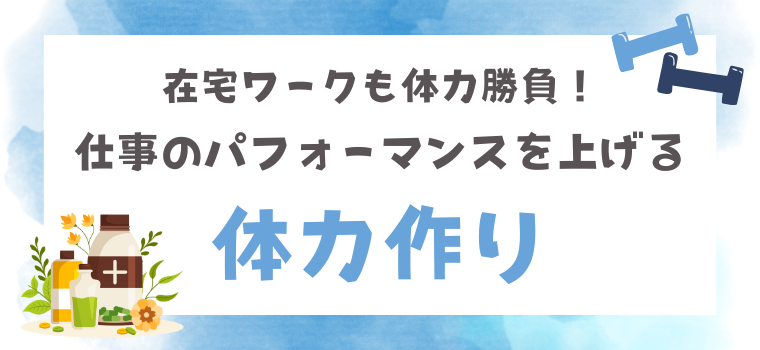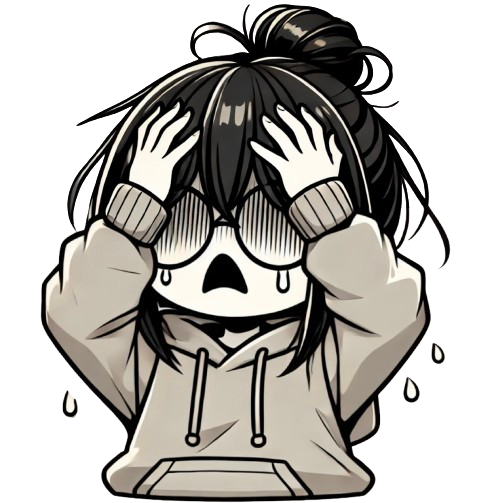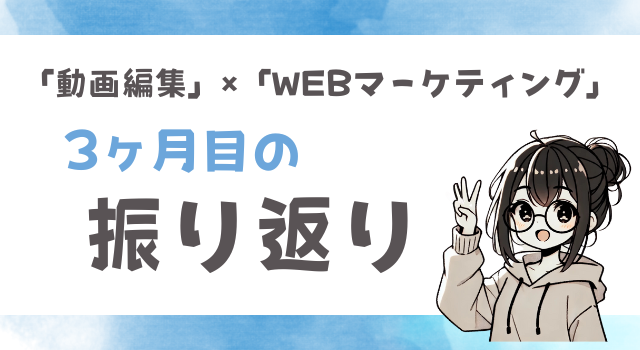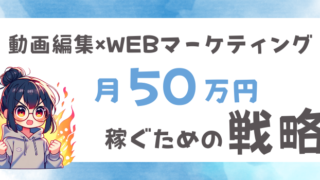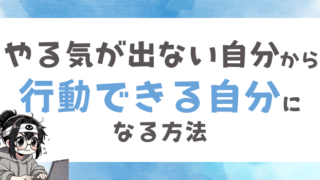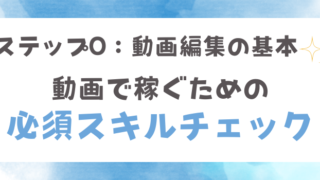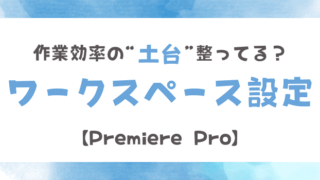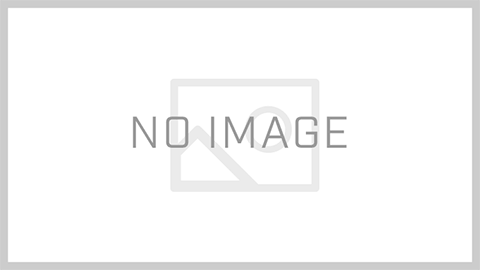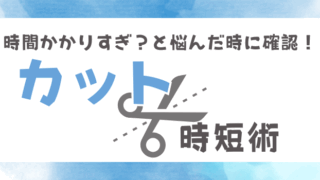そう感じることありませんか?
在宅ワークの毎日でパソコンとにらめっこ、気づけば1日中座りっぱなしなんてことにも。ふと気づいたら…
「今日ご飯とお手洗い以外で歩いてないな…」
「外出しただけで、横になりたくなる…」
「階段ちょっと上がっただけで息切れた…」
言わずもがな、運動不足です。
運動不足は、生活習慣病など健康面のリスクだけではなく、気力や集中力の低下、メンタル面にも影響します。
とはいえ、
そのままにしててもいいことはないとわかっているけど、現状の改善は後回しになっていまう現状。
でも、よくないと思っているのであれば、小さなことから改善しましょう!在宅だからこそ、「意識的に動くこと」が大切です!
今回は、運動不足とわかりつつも動けない、そんな在宅ワークで働く方が少しでも自分の身体も大切できるきっかけになれば嬉しいです。
この記事では、
運動不足による身体への恐い影響
在宅ワークこそ体力が必要な理由
今日から始められる、おすすめの簡単体力作り
この3つについて、書いていきたいと思います。危機感を感じつつ、動けないでいる人は、ぜひ最後まで読んでみてください。
運動不足による身体への恐い影響
 では、はじめに運動不足による悪い影響について。
では、はじめに運動不足による悪い影響について。
在宅ワークの前に通勤をしていた方は、職場までの通勤や、職場内の移動、帰りに買い物など自然と体を動かす状況だったと思います。
しかし、在宅ワークになると、主にパソコンを使った内容が多くを占めて、気づいたら、長時間パソコンの前で、同じ体勢で座っていることもあると思います。
・食事・家事
・お手洗い
・宅配を受け取る時
くらいしか、動かなくなった方もいるんじゃないでしょうか?
この状態が続くと、じわじわと体に負担蓄積して、一気に症状がきます。
身体的な影響
身体的な影響として、一部とはなりますが、運動不足になると体力が低下します。体力が減ることで、疲れやすくなってしまって、活動量が少なくなりさらに体力は低下する悪循環。さらに、動かなくなることで筋力や筋持久力も落ちてしまいます。
筋力が落ちることでも、動くとすぐ疲れやすくなってしまったり、姿勢も猫背が楽になって、そんことで疲労がたまりやすくなったり、肩こりや腰痛、首の原因にも繋がってきます。
他にも、筋肉量が少なくなることで、全身への血流が不足して、血行不足による、頭痛や眼精疲労、白髪、むくみ、冷えなどの原因にも…。
動かないことで基礎代謝が低下して、消費エネルギーが減ることで、太りやすくもなってしまいます。
さらに、活動量が減ることで、消費と摂取エネルギーのバランスが崩れたり、体に脂肪がたまりやすくなって肥満の原因や、その影響で高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣秒を引き起こす原因にもなってしまいます。
身体的な影響
・筋力低下(特に、足や体幹)
・血行不良
・姿勢が悪くなる(猫背、巻き肩)
・肩こりや腰痛、首の痛みの慢性化
・代謝が落ちて太りやすくなる
・生活の質が悪くなる
・生活習慣病のリスクが上がる
など
将来の健康のために、早めの意識が大切です。気づいたら、まず意識してみてください。そそして、フリーランスの方は特に、ついつい忘れがちになりますが、年1回は健康診断して数値としても確認してくださいね。
メンタルへの影響
運動は、心の健康にも影響していて、体を動かすことで「セロトニン」というホルモンが出るんですが、運動不足になるとこのホルモンが不足して、
・やる気が出ない
・気分が落ち込みやすい
・不眠気味になる
運動不足は「ただの体力の低下」だけじゃなくて、健康・体調・気分と、いろんなところに悪影響をおよぼすので、思っている以上に危険なんです。
わかってる、やばいんだよ、わかってるんだ…
在宅ワークこそ体力が必要な理由

体力作りは、健康管理だけではなく、集中力・判断力・継続力といった「仕事のパフォーマンス」を支える大事な土台です。
在宅での仕事は一見、体力を使わないように見えるけど、
・長時間同じ姿勢での作業
・画面をみ続けることで目も脳も疲れる
・いつでも仕事ができる環境だからこそ休むタイミングを逃す
といった、状況で、想像以上にエネルギーを使ってしまっています。
しかも、体力が落ちると
・すぐ疲れて集中が続かない
・頭がぼーっとしてミスが増える
・夕方にはヘトヘトで作業が止まる
・寝つきが悪くて翌日に疲れを持ち越す
という状態になって、結果的に仕事の効率が落ちてしまうことも…。
一方で、体力がついてくると――
✔ 長時間でも集中力が持続する
✔ 疲れにくく、頭が冴える
✔ リズムよく仕事が進む
✔ 心に余裕ができてポジティブになれる
「疲れない=がんばれる」ではなく、疲れにくい体=自然とパフォーマンスが上がる
在宅ワークは見た目以上に自分自身のコンディション管理が問われる働き方。
だからこそ、意識的に体力をつけることが、効率よく働くため「自分の体をどう整えるか」意識していきましょう!
在宅ワーカーのためのおすすめ7つの体力作り習慣

体力作りは、健康管理だけではなく、仕事で最高のパフォーマンスを発揮するためにも重要なこと。
在宅での作業多くなると、運動量はどうしても減るし、集中のあまりずっと続けちゃう人もいるかもしれません。
そんな時こそ、「自分の体をどう整えるか」仕事の質を上げたり、持続力をつけるためにも試してみてください!
アスリートも実践している、体調管理の5つの基本をご紹介します。
1. 朝のストレッチ
一日の始まりに、太陽の光を浴びて体内時計リセット!
人にもよりますが、在宅ワークを始めて、夜型になった人もいるのではないでしょうか?
まずは、起きたらカーテンを開けて、背筋を伸ばして深呼吸からスタート!
このとき、腕は大きく上げながら息を吸って、ゆっくり口から吐きながら腕を下ろす!
背筋を伸ばして1日を始めましょう!
2. 定期的なプチ運動
・1時間に一回は立ち上がって背伸び
長時間同じ姿勢でいると体に負担がかかって、あちこち痛みがでてくるので、1時間に1回、立ち上がって体を伸ばせるとベスト!
タイマーをかけておくことで、意識的に休憩になるので、自分の集中できる時間と合わせて25分や1時間などセットして、休みも入れていきましょう!
・腕のストレッチで、腕から首にかけての凝りをほぐす
ストレッチとして、キーボードやマウス操作で手首から肩にかけて凝り固まっているので、腕を伸ばして手を前にだし、目を閉じて、ゆっくり息を吐きながら、上を向いている中指を外回しで下に5秒キープ。(腕の上の部分が痛くなってきたら無理のない範囲で)
肩こりがひどい人は壁手をつけて伸ばすのもおすすめです!(カイロプラクティックの先生に教えてもらえいました)
・スクワット
さらに余裕があるなら、食事やお手洗いで立ったとき、歯磨きのときに、1スクワット。
3. 水分補給を意識する
・行動したら一口水を飲む習慣
気づいたら夕方に水を500mlも飲んでなかったなんてことありませんか?水分不足は集中力の低下や脱水になってしまう可能性もあるため意識してとる必要があります。
食事や手洗い前後、タイマーをかけて休憩のときなど、その都度一口水分を取ることを意識して摂っていきましょう!
ちなみに水分不足は太る原因にもなるので、最近体重計に乗って、見なかったことにした人は特に意識してみてください。
あと、コーヒーや栄養ドリンクは水分ではないです。水やノンカフェインのお茶系がいいのですが、水飲みましょう!
水分をとることで体内の循環がよくなって、疲労感を軽減にもつながります。
4. 間食の量と時間に気を付ける
ついついお菓子摘んでませんか…?在宅ワーク、間食が増えがちです。
過剰な資質や糖質を取りすぎてしまうことで肥満の原因や、食生活飲みだれにつながってしまうので、カロリー量は見ておくといいです。間違えても袋そのままパソコンの横におくのは危険です。
1日の摂取カロリー目安(活動量が少ない場合)
摂取カロリー = 体重(kg) × 基礎代謝量(kcal/kg)
基礎代謝:男性25(kcal)、女性23(kcal)
| 体重 | 男性の目安(kcal) | 女性の目安(kcal) |
|---|---|---|
| 50kg | 1250kcal | 1150kcal |
| 55kg | 1375kcal | 1265kcal |
| 60kg | 1500kcal | 1380kcal |
| 65kg | 1625kcal | 1495kcal |
このカロリーは「最低限、生きていくためのカロリー+日常動作レベル」の数値のため、運動を取り入れている人は+200〜400kcal
極端に下回ると「栄養不足→代謝が落ちる→痩せにくい・疲れやすい」悪循環になるので注意!
おやつは時間と量を決めて、寝る3時間前は控えめに。
ダラダラ食べが本当に危険で、気づいたらえらいことになります。
朝起きたときやお風呂前の体重測定で意識することもおすすめです!
5. 睡眠環境を整える
在宅ワークのほとんどはパソコン作業が多いので、目を休めてあげてください。
疲れてすぐ寝てしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、体や目を休めるためにも、
就寝直前のスマホを控えて、質の良い睡眠を確保して体を休めてあげましょう。
睡眠時間は納期前の修羅場でないなら、7〜8時間取った方が、仕事が捗ります。
6. 仕事時の姿勢を整える
パソコン操作では、同じ体勢や座っている時間が長いことが多いので、注意が必要。骨の歪みや血行不良などによるも不調につながって、慢性的な肩こりや腰痛、頭痛に。
ベストは、作業に適した椅子や高さのあった机やモニターの位置に仕事環境を整えること。
難しい場合には、気づいた時でもいいので背筋を伸ばして、座りっぱなしを避けましょう。
でもできれば、在宅ワークで働いていくのであれば、椅子や机も投資する価値ありです。長く働くなら快適さとパフォーマンスは重要。
7. コミュニケーションをとる
在宅ワークでは孤独感やストレスを貯めやすくなります。
軽減するために、定期的に家族や友人とのコミュニケーションを取るなど、
心の健康を大切にしましょう。
同じく在宅ワークを頑張っている仲間のいる環境や、全く違う職種の人と話すと気持ちがリセットされるので、気分転換のためにも話すことも意識してみてください。
在宅ワークは自由な反面、自分で体調を整える力も必要で、それも仕事の一環だと思います。
だからこそ、
・小さな運動習慣
・意識的なリズム作り
・自分の身体への気づきと労り
意識をしていって、健康も仕事の質も上げていきましょう!
オススメサプリメント

それでも食事や基礎体力を整えてあげるのに、サプリメントを活用するのも一つの手です。栄養バランスが毎日いいとも言えず、総合ビタミンを飲み始めたのですが、疲れやすさが大分減った感じがします。
おすすめのアプリを紹介していきます。
体の基盤を整える:トータルビタミン
ビタミンには、エネルギー源となる三大栄養素(炭水化物、たんぱく質、脂質)
の働きをサポートする働きがあります。
しかし、バランスよくとらなければ一番少ない量にまでしか働かず
残りは排出されてしまいます。
そのため、不足しているビタミンを摂取することで全体的な底上げを図ります。
しかし、自分で足りていないビタミンは…と毎日気にすることも大変です。
ですのでトータルビタミンで揃っているものをでもとの基盤を
整えてあげるのも一つの方法です。
ナイアシンアミド:体の錆を落とす
今までの生活や年齢を重ねることで、私たちの体は錆付いていっています(酸化)。
ナイアシン(ビタミンB3)は、抗炎症作用を持ち、
体内の不要な物質をだして、新陳代謝を促進する働きを持ちます。
その効果を利用したのが「ナイアシンフラッシュ」です。
ナイアシンフラッシュとは、末梢血管が拡張され、皮膚が赤くなりほてりや痒みを感じる現象で、一般的には副作用とされています。
副作用の程度は個人差があり、症状は発症後数時間で元に戻り、
通常は1週間程度で体が慣れ出なくなることが一般的です。
ビタミンBであり、不要な分は排出されるので、
健康への影響はないとされています。
ちなみに私は大分錆びついていたのか、初日はめまいと吐き気があり、
少しお休みしてから再開して1か月ほど痒みが続きました。
以降は食べ過ぎた時など痒みがでますが、ほとんど症状はなくなりました。
ビタミンC:腸内環境を整える
腸は第二の脳といわれて入れています。
腸内環境が乱れているとアレルギーや免疫力、肥満や肌、精神状態など
体の様々な部位分に影響し、体のパフォーマンスが悪くなってしまいます。
改善するための一つに腸内に排便が残った状態(宿便)を出すことで
解消する方法がご紹介する、ビタミンCフラッシュです。
ビタミンCを一度に大量摂取すると腸での許容量を超えることで
体内に吸収されないまま水便として排出されます。
腸内をデトックスできる免疫力を高め、腸内環境を改善する効果があります。
ビタミンCも不要な分は排出されるため副作用はないとされています。
また、便秘の原因としてマグネシウム不足もあるので、
不足している場合は補充することをおススメします。
筋肉をサポート:プロテイン
筋肉は、私たちの日常活動や運動をサポートするだけでなく、
基礎代謝を高めて健康を維持したり体力を向上する重要な役割を担います。
定期的な筋肉トレーニングが困難だったり、タンパク質の摂取が不足している
と感じている場合はには気軽に摂れるものから取り入れてみましょう。
さらに、日本人はタンパク質不足であることが多いです。
一日の必要量は体重×1g
といわれていますので、毎日食事だけで補うのはなかなか難しいです。
その補充や、また、余計な空腹感がなくなることで間食も控えられるので、
内臓への負担も減らすことができるので上手くのんでいくといいです。
おわりに
在宅ワークでは、自分自身で体調や生活リズムを管理する力が大切になります。特にフリーランスリャ副業でお仕事をしている人にとって、体力は「働き続ける土台」。どんなにスキルがあっても、健康を崩してしまっては本末転倒です。
体調管理や体力の意地ができれば
・安定したパフォーマンス
・集中力・持続力アップ
・心のゆとり
にも繋がって、結果的に仕事の質が上がって、収入アップにもつながります。
めんどくさいなの気持ちがあるかもしれませんが、今日できる小さなことからやってみるのでもいいです!そして、やった自分をたくさん褒めてあげてください。
ここまで読んでくださりありがとうございました!
この記事が少しでも、在宅ワーカーさんの健康づくりや習慣の見直しのきっかけになったら嬉しいです。
次の記事でも、またお会いできることを楽しみにしています!